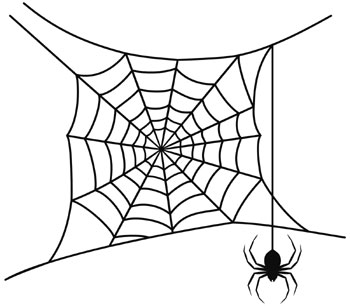昆虫シリーズ70 節足動物・クモの仲間
昆虫ではないクモの仲間 ウィキメディア・コモンズ )
INDEX クモの巣と「かすみ網」、クモに共通する特徴、♀が♂を食べる共食い、クモの巣の張り方、無駄のないリサイクル、糸の振動から情報を得る、鋼鉄の5倍も強いクモの糸、ギンナガゴミグモ、ナガコガネグモ、コガネグモ、ジョロウグモ、オオジョロウグモ、オニグモ、ギンメッキゴミグモ、クサグモ、コクサグモ、ジグモ、ハナグモ、コハナグモ、ササグモ、ハエトリグモの仲間、アオオビハエトリ、マミジロハエトリ、ムツボシオニグモ、トリノフンダマシ、オオヒメグモ、ワカバグモ、ヤミイロカニグモ、ワキグロサツマノミダマシ、イオウイロハシリグモ、スジアカハシリグモ、アリの真似をするアリグモ
クモの巣と「かすみ網」 ・・・クモは、虫がよく飛んでくる場所に網のような巣を張っておいて、虫が引っ掛かるのをじっと待つ。それを真似たのが、昔、小鳥を捕まえるために使った「かすみ網」。細い糸で作った目に見えない網を、渡り鳥が通る所に張っておいて、たくさん捕まえた。今では禁止されている。
網を張るクモ ・・・ジョロウグモ、コガネグモ、オニグモなど、網を張ってエサを捕る種類がほとんどだと思っていたが、その割合は全体の半分ほどと意外に少ない。
網を張らないクモ ・・・網を張っていたクモの一部が、それを捨てる方向に進化したハエトリグモ、コモリグモ、カニグモなど。お尻から糸は出る。木の葉の上から落ちたりする時、ツーッと命綱のように使ってぶら下がりながら降りる。
クモに共通する特徴
糸を使うことに最も長けていること 。クモは何種類もの糸を網を作ったり、捕まえたエサを巻き上げたり、卵を包んだり、命綱にするなど、目的に合わせて使い分けする。
昆虫を中心とした肉食であること 。共食いもする。♀が求愛してきた♂を、交尾前後に食べてしまうことも有名。
♀が♂を食べる共食い ・・・♀はたくさん食べて卵を多く作ることが必要だから、食べられるものなら何でも食べる。自分と同じ種類でも容赦しない。♀から見れば、言い寄ってきた♂は、食べ物として大変魅力的に見えるらしい。実際、♂を食った♀の産む子は生存率が高くなることが分かっているという。種によって90%近く食べられるものから、ほとんど食べられないものまで様々。
クモの巣の張り方
最初の1本は、風を利用する。お尻の先から糸を出し、風になびかせる。すると、糸の端が離れた木の枝などにくっつく。それを辿って丈夫な橋糸をかける。
その橋糸を真ん中あたりから、体重を利用して糸を出しながら降りていく。こうしてY字型に糸を張る。
次に枠糸と縦糸を張る。そして中心から足場糸を渦巻き状に張る。
粘らない足場糸や縦糸を伝わって、外側から中心に向かって横糸を張る。横糸を張りながら、必要がなくなった足場糸ははがしてしまう。よく粘る横糸が獲物を捕らえるのに役立つ。
クモは毎日、網を張り直す・・・一日の終わりになると、糸はボロボロになって性能が落ちるので、横糸全部と縦糸の大部分を回収し、次の日の始めに一から張り直す。これを毎日繰り返す。
VIDEO
参考動画:クモの巣作りの一周(オニグモ)糸の張り方が凄すぎる! - YouTube
クモは自分の張った巣にどうして絡まないのか?
なぜ円網の下半分が大きいのか? ・・・重力を考えると、下にエサがかかった方が素早く移動できるので都合が良い。だから下半分を大きくつくり、下を向いてエサを待つ。エサがたくさん捕れると、翌日はより大きな網を張ってさらに捕獲数を増やそうとする。まさに待ち伏せ型狩りの名人。
無駄のないリサイクル ・・・糸を毎日張り替えるのは、もったいないと思う。ところが、糸はたん白質でできているので、古い糸を食べ、巣を張り替える時は、お腹の中でもう一度新しい糸の材料にする。つまり、無駄にしないようリサイクルする。自然界では、無駄なことをしない者が勝ち残るようにできている。無駄がやたら多い人間こそ、昆虫に学ぶべきだと思う。
糸の振動から情報を得る ・・・クモは、網にかかった獲物がもがく糸の振動で、獲物がかかったことを知る。落ち葉などが網にかかっても獲物とは思わない。あくまで網を振動させ続けるものに反応する。
クモの巣に虫が引っ掛かると ・・・逃げようとしても、もがけばもがくほどくっついて、体にまとわりつく。そして、大きなクモがスルスルと現れ、お尻から糸を出すと、獲物の体をグルグル巻きにしてしまう 。身動きできなくすると、その体の一点をちょっとかむ。こうして消化液を注入して、獲物の身体を溶かすと、ゆっくり吸う。これを体外消化という。
クモより数倍大きいカマキリが掛ると ・・・ファーブルの観察によれば、クモは、少し離れた所からカマキリにお尻を向けると、後脚を使って、白いシーツのようなものを引き出し、投げ掛けた。これはたくさんの糸をまとめて作った布のようなもの。さすがのカマキリも、このべったりくっつくシーツに包まれると、身動きができなくなる。クモの勝ちである。
鋼鉄の5倍も強いクモの糸 ・・・クモの糸は、カイコの作る糸の成分の一つであるフィブロインというタンパク質から出来ている。カイコの糸に比べて、切れ難く、弾力性があり、熱や紫外線にも強い。同じ太さの鋼鉄の約5倍もの強さがあるが、重さは1/5ほどしかない。例えば、直径1mmの糸で、約100kgの重さでも切れない。直径1cmの糸で網をつくれば、ジェット機でも支えられると言われるほどの強さには心底驚かされる。
ギンナガゴミグモ (コガネグモ科)ウィキメディア・コモンズ )
おびき寄せの術「隠れ帯」 隠れ帯は、太陽光を受けて紫外線をよく反射する 。このため、紫外線に誘引される性質がある一部の昆虫が網に引き寄せられると考えられている。実際、隠れ帯がつけた網と、そうでない網の捕獲数を比べると、隠れ帯がついた網の方がより多くの昆虫を捕獲したことが分かっているという。つまり隠れ帯は、獲物をおびき寄せ、網にかかる獲物の量を増やす効果がある ということ。ただし、クモを専門に食べるハチやクモなどの捕食者までおびき寄せるデメリットもある。 (写真出典:ウィキメディア・コモンズ )
ナガコガネグモ (コガネグモ科)
VIDEO
参考動画:【閲覧注意】ナガコガネグモ の美しい「卵の袋」には約1000個の卵が入っている!巣作りからふ化した子どもが飛び去っていく瞬間までを撮影【どうぶつ奇想天外/WAKUWAKU】 - YouTube
巣 ・・・草の間や低木などの低い場所に地面と垂直に美しい円形の網を張る。網には、ジグザグ模様の1本の太い帯・隠れ帯がつくられ、その真ん中で頭を下にして獲物を待ち構えている。
幼体がつくる隠れ帯 ・・・楕円形に白いジグザグ模様の隠れ帯をつくる。
VIDEO
参考動画:早業 ナガコガネグモが、キンケハラナガツチバチを捕獲 - YouTube
コガネグモ (コガネグモ科)
VIDEO
参考動画:30秒の心象風景16755・巣の中央に~コガネグモ~ - YouTube
巣 ・・・背の高い草の間に垂直円網をつける。X字型やその一部を省略した隠れ帯 をつくる。
VIDEO
獲物に糸をかけるコガネグモ ・・・第4脚を使って大量の糸を引き出し、獲物をグルグル巻きにして捕食する。
ジョロウグモ (ジョロウグモ科)
VIDEO
巣 ・・・縦糸・横糸の本数が多く、目が非常に細かい。縦糸は途中で分岐する。円網の前後にバリアー網がある三層構造の巨大な網を張る。
VIDEO
参考動画:糸を紡ぐジョロウグモ (巣を張る蜘蛛) - YouTube
食性 ・・・大型のチョウやガ、セミ、スズメバチ、トンボ、果ては同種の♂も捕食する。
日本最大のオオジョロウグモ (ジョロウグモ科)
VIDEO
参考動画:オオジョロウグモの交尾 - YouTube
巣 ・・・長径1.5mに及ぶ非常に大きな円網を張る。鳥やコウモリも捕らえる ことがある。幼体の網は二重構造で、網の前方にバリアー網を設ける。
オニグモ (コガネグモ科)
VIDEO
巣・・・頑丈な縦糸と粘性を持つ横糸からなる典型的な垂直円網。主に夜に張るが、昼に網が残っていることもある。サイズは非常に小さい。
ギンメッキゴミグモ (コガネグモ科)
巣 ・・・垂直円網。円網は、通常、クモがいる位置より下の面積が広いが、上を向いて網に止まる本種は、上の面積が広くなっている。
クサグモ (タナグモ科)
VIDEO
参考動画:リンゴカミキリを捉えたクサグモ Agelena limbata - YouTube
巣 ・・・公園や道路沿いの植え込みや人家の庭木などが、薄いシートのようなクモの巣に一面覆われていることがある。その巣は、クサグモが編んだ巣である。巣の表面は、細い糸が張り巡らされ、その隅には糸でつくられたトンネルがある。トンネルの先は巣の外に通じていて、敵に襲われた時の逃げ道にもなる。網のシートには粘り気がなく、網に虫が入り込んだり、糸に引っ掛かったりする。クサグモは、昼間はトンネルに潜み、夕方になるとシートの上を歩き回って、獲物を捕まえて食べる。
コクサグモ (タナグモ科)
ジグモ (ジグモ科)
巣 ・・・地中から地上部に延びた袋状の巣をつくる。地面を歩く獲物が袋に触れると、大きな上顎で袋ごと獲物に噛みつき、そのまま中に引き込む。
VIDEO
参考動画:おもしろ科学実験 観察 ジグモを捕まえてみよう - YouTube
ハナグモ (カニグモ科)
VIDEO
参考動画:ミツバチ ハナグモに捕まる - YouTube
VIDEO
参考動画:愛嬌のある模様 ハナグモ Misumenops tricuspidatus カニグモ科 蜘蛛 spider - YouTube
花で待ち伏せ ・・・その名のとおり、花の吸蜜に来る昆虫を狙って、花や葉の上でで待ち伏せすることが多い。
コハナグモ (カニグモ科)中央に2~3対の黒点 がある。ハナグモに似ているが、腹部に黒点があることや、頭胸部の毛が目立つことで識別できる。平地から山地まで広く生息し、草地や林縁で見られる。夏から秋に見られる。全国に分布。
ササグモ (ササグモ科)
VIDEO
ハエトリグモの仲間 ・・・その名のとおり、ハエなどの昆虫を捕食する。
VIDEO
参考動画:ハエトリグモの捕食シーンまとめ集! - YouTube
日本では105種が確認されている。眼が大きく発達していて、前列に4つの眼が正面を向いている。 地面を歩き回って獲物を見つけ、ジャンプして襲い掛かる。夜間は糸で巣をつくって休む。
VIDEO
参考動画:人懐こいハエトリグモ - YouTube
アオオビハエトリ (ハエトリグモ科)
マミジロハエトリ (ハエトリグモ科)
ムツボシオニグモ (コガネグモ科)
トリノフンダマシ (コガネグモ科)・・・日中、葉の裏などで脚を縮めてじっとしていると、その姿が鳥の糞に似ていることが名前の由来。夕方から夜にかけて動き出すと、脚が全て現れるので、クモであることが分かる。
VIDEO
参考動画:陽が当たり動き出したトリノフンダマシ Cyrtarachne bufo ♀ - YouTube
オオヒメグモ (ヒメグモ科)
ワカバグモ (カニグモ科)
草地や林縁などの葉や花の上でハエやハチなどの昆虫を待ち伏せする。
VIDEO
参考動画:ワカバグモ(蜘蛛)がアブを捕食吸汁 - YouTube
ヤミイロカニグモ (カニグモ科)
VIDEO
参考動画:ヤミイロカニグモ♀(蜘蛛)がヒメハナバチ♀を捕食 - YouTube
ワキグロサツマノミダマシ (コガネグモ科)
イオウイロハシリグモ (キシダグモ科)
スジアカハシリグモ (キシダグモ科)
アリの真似をするアリグモ (ハエトリグモ科)
VIDEO
参考動画:アリに擬態したアリグモ - YouTube
なぜアリの真似をするのだろうか?
参 考 文 献
「クモハンドブック」(馬場友希・谷川明男、文一総合出版)
「クモの巣ハンドブック」(馬場友希ほか、文一総合出版)
「クモのイト」(中田兼介、ミシマ社)
「クモはなぜ糸から落ちないのか」(大崎茂芳、PHP新書)
「ファーブル先生の昆虫教室」(奥本大三郎、ポプラ社)
「すごい自然図鑑」(PHP)
「ずかん 虫の巣」(監修・岡島秀治、技術評論社)
「昆虫の生態図鑑」(学研)
「講談社の動く図鑑 move昆虫」(講談社)